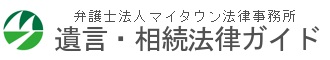【第5回】特別受益
第5回は、「特別受益」です。
相続人の中に、①遺言によって被相続人から無償で財産を譲り受けた者がいる場合(遺贈)や、②生前贈与を受けた者がいる場合、相続人間の公平を図るための制度が、「特別受益」です。
具体的には、「特別受益」に該当する生前贈与等があった場合、被相続人の遺産の額(借金は控除しません。)に生前贈与等の額を加算したものを、遺産とみなします(なお、相続人以外の第三者への生前贈与や遺贈は、遺産に含まれません。)。当該みなし相続財産を基礎に、相続人の相続分を計算して、特別受益を受けた相続人については、相続分から特別受益を控除することになります。
例えば、被相続人Aが死亡し、相続人は、子であるB、C、Dの場合を考えてみましょう。遺産は5000万円で、Aは、Bに対し、婚姻の際の持参金として、400万円を生前贈与していたとします。
① まず、遺産5000万円+400万円=5400万円が、みなし相続財産となります。
② 各相続人の相続分は、5400万円÷3人=1800万円です。
③ Bだけは「特別受益」分を控除するので、1800万円-400万円=1400万円となります。
④ 最終的に、B1400万円、C1800万円、D1800万円となります(合計5000万円)。
以上のように、「特別受益」を受けたBの取り分を少なくし、相続人間の公平を図るための制度が「特別受益」なのです。それでは、何が「特別受益」となるのか見ていきましょう。
特別受益の種類
遺贈
遺贈とは、遺言によって、被相続人から相続人等に対し、無償で財産を譲渡することです。後述の生前贈与と異なり、遺贈の場合は、遺贈の目的にかかわらず、特別受益になります。
また、「相続させる」旨の遺言も、特別受益になります。
生前贈与
生前贈与は、遺産の前渡しとしての趣旨であれば、特別受益となります。具体的には、以下の2つの種類があります。
婚姻もしくは養子縁組のための贈与
ア 持参金
相続人の婚姻等の際、被相続人が持参金等を贈与していることがあります。一般的に、持参金は特別受益にあたります。ただし、少額で、相続人に対する扶養の範囲内と認められる場合には、特別受益にはあたりません。
イ 挙式費用
一般的には、親の世間に対する社交上の出費という性質が強いため、特別受益にあたりません。もっとも、結婚式の招待客のほとんどが婚姻当事者の知人の場合等には、特別受益にあたる可能性があります。
ウ 結納金
説が分かれています。特別受益にあたらないとする見解が多いと思われます。結納金の性質につき、親族間の情誼を厚くする儀式上の出費と考えれば、特別受益にあたりません。他方、婚姻のために必要な出費と考えれば、特別受益にあたると思われます。
生計の資本としての贈与
生計の基礎として役立つ贈与を意味します。これは、かなり広い意味に解釈されています。
例えば、不動産の贈与、営業資金の贈与などです。遺産の前渡しと認められる程度に高額な贈与は、原則として特別受益になると考えられます。遊興費のための贈与は、特別受益にあたりません。
ア 教育費
私立医学部のように、特に多額な教育費でない限り、特別受益にはあたらないことが多いといえます。
イ 少額の贈与が多数回あった場合
1回あたりの贈与は少額だが、贈与が多数回なされ、総額が多額になる場合があります。この場合、親族間の扶養義務の範囲を超える部分は、特別受益にあたります。
ウ 借金を代わりに払った場合
被相続人が相続人の借金を代わりに払った場合、被相続人は、相続人に対し、代わりに払った金額の求償をすることができます(この求償権も相続の対象になります。)。そのため、原則、相続人に対する贈与はないことになります。
もっとも、被相続人が求償権を放棄し、相続人に対して求償しないことも多いです。このように、被相続人が求償権を放棄したと認められる場合には、代わりに支払った金額いかん等によって、特別受益にあたる可能性があります。
エ 稼働できない子に対する贈与
身体的要因又は精神的要因等により、稼働できない子に対する贈与は、親の扶養義務の範囲内と考えられるので、特別受益にあたらないと考えられます。
オ 生命保険金
被相続人が契約していた生命保険につき、相続人の1人が受取人と指定されていたとしても、原則として、生命保険金は特別受益にあたりません。
もっとも、保険金の金額、遺産総額(生命保険金を含みません。)に対する割合、被相続人に対する介護の貢献の度合い等を考慮して、相続人間の不公平が特別受益(民法903条)の趣旨に照らし到底是認することができないほど著しい場合には、特別受益に準じて扱うことになります。この場合、保険金のうち、全保険料に対して被相続人が支払った保険料の割合に相当する部分を、特別受益に準じて扱うことになります。
保険金額の遺産総額に対する割合がどの程度になれば、特別受益として扱うべきかにつき、具体的な基準はありません。もっとも、保険金額が遺産総額の少なくとも3分の1を超える場合には、特別受益として扱う方向で考える必要があると思われます。
なお、掛け捨て型よりも貯蓄型生命保険の方が特別受益にあたる可能性が高いといえます。
カ 死亡退職金
死亡退職金の性質は退職金支給規定等の内容によるので、その内容を確認して、特別受益にあたるか否かを判断することになります。一般的には、死亡退職金は受取人の生活保障を目的としたものなので、特別受益にはあたらないと考えられます。
もっとも、別の見解もあり、死亡退職金の功労報償的な性格が強い場合には特別受益にあたり、遺族の生活保障としての性格が強い場合には特別受益にあたらないとする考えもあります。
逆に、死亡退職金の功労報償的な性格が強い場合には特別受益にあたらず、遺族の生活保障としての性格が強い場合には特別受益にあたるとする考えもあります。
キ 遺族給付
遺族給付が特別受益にあたるか否かについては、肯定説と否定説があります。特別受益にあたらないとする考え方が多いと思われます。
ク 借地権
【借地権の贈与】
被相続人が有していた借地権を相続人の1人に贈与する場合、特別受益にあたります。
【借地権の設定】
被相続人の土地上に、相続人が、建物を建てるため、借地権を設定した場合、相続人が対価(権利金)を支払っていない場合には、借地権の設定は、特別受益にあたります。対価は一括でない場合もあり、通常の賃料に対価を上乗せする場合もあります。
これに対し、相続人が借地権設定の対価として、権利金を支払っている場合には、特別受益にあたりません。
ケ 底地を相続人が買った場合
被相続人が借地権を有している土地について、相続人が地主から底地を買うことがあります。
例えば、更地価格3000万円の土地に、被相続人の借地権(1800万円)が設定されている場合、相続人がこの土地を1200万円で買うような場合です。この場合、被相続人と相続人の間で、被相続人の借地権を消滅させ、相続人が完全な所有権を取得する合意をすることがあります。合意がある場合には、実質的に、相続人は、被相続人から借地権を贈与されたことになります。そのため、実質的な借家権の贈与が、特別受益にあたることになります。
これに対し、借地権が消滅していない場合には、地主となった相続人が、被相続人に対して、借地料や更新料を請求することが考えられます。
コ 土地の無償使用(使用貸借)
被相続人の死亡時、被相続人が所有する土地の上に、相続人の1人が建物を建て、被相続人の土地を無償で使用している場合があります。この場合、土地の使用借権の生前贈与があったといえるので、使用借権相当額(土地の1割~2割程度)が特別受益にあたります。
他方、特別受益の額に関し、上記とは異なり、地代相当額が特別受益にあたるとの主張がしばしばなされます。しかし、相続人が土地を無償で使用しなければ、被相続人が当然第三者に土地を貸して賃料を得ていたことが立証できない限り、地代相当額が特別受益にあたるとの主張は認められないと思われます。
なお、土地を使用する代わりに、被相続人の面倒を見る等の負担を負っていた場合には、無償で土地を使用していたとはいえないので、特別受益にあたらないと考えられます。また、相続人が土地の固定資産税を支払ってきた等の事情がある場合には、相続人が、特別受益を考慮する必要がないという意思表示をしていた(後述の持戻し免除の意思表示)と認められることが多いと思われます。
サ 建物の無償使用(使用貸借)
被相続人が所有する建物を、相続人の1人が無償で使用していた場合でも、建物の使用借権の経済的価値は低いため、一般的には、特別受益にあたりません(反対説はあります。
)。 もっとも、相続人が建物を無償で使用しなければ、被相続人が当然第三者に建物を貸して賃料を得ていたと言える場合には、賃料相当額等が特別受益にあたる可能性があります。
なお、相続人の1人が被相続人と同居していたが、独立の占有権原があるとは言えない場合には、特別受益にあたりません。