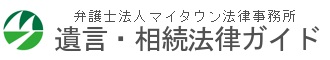寄与分の代表的な態様
家業従事型
被相続人の家業(農業、医師等)に従事する場合です。営利事業に限られません。
先程お話ししたとおり、寄与分が認められるためには、①寄与が「特別の寄与」であること、②被相続人の財産が維持又は増加したことが必要です。
特別の寄与
家業従事型の場合、特別の寄与といえるためには、ア、特別の貢献 イ、無償性 ウ、継続性 エ、専従性が必要です。
ア 特別の貢献
夫婦間の扶助義務や、親族間の扶養義務の範囲を超えた特別の貢献が必要です。
イ 無償性
寄与にある程度見合った対価が支払われたときは、寄与分は認められません。これに対し、報いられていない部分があるときは、寄与分が認められる可能性があります。
ウ 継続性
約3~4年、家業に従事することが必要であるとする見解があります。
エ 専従性
家業に専念することまでは不要です。もっとも、時々家業を手伝っていただけでは足りず、相当の負担があったことが必要です。
相続人の財産が維持又は増加したこと
被相続人の経営する会社への従事
被相続人ではなく、被相続人が経営する会社に従事した場合、原則として寄与分は認められません。
もっとも、被相続人と被相続人が経営する会社とが経済的に極めて密接な関係にあり、会社への従事が被相続人の財産の維持又は増加と明確に関連している場合には、寄与分が認められる可能性があります。
寄与分の評価
家業従事型の寄与分の評価方法は、「寄与行為に関する相続開始時における標準的な報酬額×(1-生活費控除割合)×寄与の期間」です。
標準的な報酬額は、家業と同種同規模の事業における同年齢層の給与額を参考にします。具体的には、厚生労働省の賃金構造基本統計調査等を参考にします。
生活費を控除するのは、寄与をした相続人の生活費が家業収入の中から支出されていることが多いからです。生活費を自分で支払っていた場合には、生活費を控除しません。生活費控除率は、交通事故事案の場合に用いられる3割~5割の控除率を用いることもあります。
なお、寄与の結果、特定の相続財産の維持又は増加に貢献した場合には、当該相続財産の一定割合をもって寄与と評価したほうが適切な場合もあります。
上記の方法で算出した額に加えて、配偶者の法定相続分は家事労働や夫婦間の扶助義務を前提としたものであること等の一切の事情を考慮して、寄与分の額を定めることになります。例えば、約10年以上家業に従事した場合に、遺産総額の10%~30%の寄与分が認められることもあります。なお、共同経営の場合には、標準的な報酬額+利益配分額が基準となります。
金銭等出資型
被相続人に対して、金銭等を贈与する場合です。①寄与が「特別の寄与」であること、②被相続人の財産が維持又は増加したことが必要です。継続性と専従性は不要です。
特別の寄与
ア 特別の貢献
イ 無償性
金銭等の出資が、無償又はそれに近い形でなされることが必要です。
相続人の財産が維持又は増加したこと
寄与分の評価
金銭等出資型の寄与分の評価方法は、「出資した財産の相続開始時における時価×裁量割合」です。
裁量割合とは、一切の事情を考慮して、裁判官が寄与分の額を調整するものです。例えば、裁量割合を0.7として、寄与分を減じること等があります。
出資した財産全額が寄与分として認められるのではなく、相続人と被相続人の身分関係、財産の種類及び価額、出資の理由、出資された財産の利用方法、出資時から相続開始時までの期間等、一切の事情を考慮して、出資の全部又は一部が寄与分として認められることになります。
なお、不動産を無償で貸した場合には、賃料相当額に使用期間を乗じた金額、融資の場合は、利息相当額が寄与分として認められる可能性があります。融資については、銀行等から融資が受けられない状況で融資し、そのおかげで事業が持ち直した場合には、利息以上の寄与分が認められる可能性があります。
療養看護型
疾病、認知症、高齢による動作困難等の被相続人の療養看護をした場合です。徘徊等のおそれがある被相続人に対する見守りも含まれます。①寄与が「特別の寄与」であること、②被相続人の財産が維持又は増加したことが必要です。
特別の寄与
ア 療養看護の必要性
①療養看護の必要性と、②近親者による療養看護の必要性の両方が必要です。
イ 特別の貢献
ウ 無償性
エ 継続性
1年以上、被相続人の療養看護をしたことが必要であるとする見解があります。
オ 専従性
相続人の財産が維持又は増加したこと
療養看護をしたことによって、職業看護人に支払う費用を節約できたといえることが必要です。精神的な援助のみでは寄与分は認められません。
要介護度
寄与分が認められるためには、要介護2以上の状態にあることが目安となります(注意すべきなのは、要介護度は身体機能に着目したものが多く、精神機能を反映していない場合があることです。)。
もっとも、要介護1であれば寄与分は全く認められず、要介護2であれば寄与分が認められるとすれば、要介護2の寄与分の評価額は、要介護2の報酬相当額から要介護1の報酬相当額を控除すべきとする見解もあります。
介護保険制度が施行される平成12年3月以前の寄与については、診断書、カルテ、日記、写真等を参考に、要介護度を推認することになります。
寄与分の評価
療養看護型の寄与分の評価方法は、「療養看護の報酬相当額×看護日数×裁量割合」です。
療養看護の報酬相当額は、例えば、訪問介護における介護報酬基準額に基づき、介護報酬単価表と要介護基準時間表を用いて算出する等します。
療養看護の報酬相当額は、有資格者の報酬相当額を参考にしたものであること、介護機関への支払額であって介護者自身の報酬ではないこと、扶養義務を負わない者への報酬であること等の理由から、そのまま寄与分の金額として評価することはできません。そのため、「裁量割合」として、通常、0.5~0.8の割合を乗じることによって調整がされます。0.7が平均と思われます。
深夜に看護した場合には、裁量割合で調整されることが多いです。
無償で建物に居住していた場合等
被相続人の療養看護をする代わりに、近くの被相続人所有の建物に無償で居住していた場合等、居住の利益がある場合には、それを控除した額が寄与分となります。もっとも、療養看護のため近くに居住せざるを得なかった場合等は、居住の利益は小さくなると考えられます。
被相続人に代わって療養看護をした場合
被相続人が扶養義務を負う者(配偶者、未成熟の子、直系血族、兄弟姉妹等)が、扶養を必要とする状態にあり、被相続人も扶養可能な状況で、被相続人の代わりに療養看護を行ったり、療養看護費用を支出する場合があります。この場合には、寄与分が認められる可能性があります。
扶養型
被相続人を扶養した結果、被相続人が出費を免れた場合です。①寄与が「特別の寄与」であること、②被相続人の財産が維持又は増加したことが必要です。
特別の寄与
ア 扶養の必要性
この場合には、疾病の存在は不要です。
イ 特別の貢献
扶養義務がないのに扶養を行った場合や、扶養義務の範囲を著しく超えて扶養した場合が挙げられます。この場合の扶養義務の範囲は、後述の扶養料の求償請求の場合と異なり、各相続人の経済状態に応分する必要はなく、法定相続分の割合で考えれば足りるとする見解が多数です。
ウ 無償性
エ 継続性
わずかな期間では足りず、相当期間扶養したことが必要です。
被相続人の財産が維持又は増加したこと
寄与分の評価
扶養型の寄与分の評価方法は、「扶養のために支出した金額×裁量割合」です。扶養のために支出した金額は、生活保護基準(生活保護手帳に記載)や、総務省の家計調査を参考にすることもあります。
裁量割合は、一切の事情が考慮されます。裁量割合が「1-寄与した相続人の法定相続分」となることもあります。
扶養料の求償請求との関係
上記の寄与分の主張とは別に、自らの扶養義務を超えて被相続人を扶養した者は、他の扶養義務者に対して、各自の経済状態に応分した求償請求をすることができます。
①寄与分としての主張と②求償請求のいずれかを選択できるのです。
なお、扶養型の寄与分の主張が認められなかった後、扶養料の求償請求を求める審判を申し立てることができるか否かにつき、紛争の蒸し返しにはあたらないとした裁判例があります。
財産管理型
例えば、被相続人の不動産の管理をした場合等です。①寄与が「特別の寄与」であること、②被相続人の財産が維持又は増加したことが必要です。
特別の寄与
ア 財産管理の必要性
例えば、所有するアパートについて管理会社がある場合に、相続人の1人が定期的に掃除をした程度では、寄与分は認められません。
イ 特別の貢献
ウ 無償性
エ 継続性
財産管理を相当期間したことが必要です。
被相続人の財産が維持又は増加したこと
寄与分の評価
財産管理型の寄与分の評価方法は、「第三者に委託した場合の報酬相当額×裁量割合」です。
例えば、建物修理等はリフォーム業者の標準工事費用、庭木の剪定等はシルバー人材派遣センター等の料金、賃貸不動産の管理は不動産会社の請負料等を参考にします。
被相続人の資金運用
被相続人の資金を運用して、資産が増えた場合であっても、寄与分は認められません。
資金運用にはリスクがあるので、リスクを負担しないまま利益だけを寄与分として主張することは許されないのです。
その他
相続放棄
例えば、Aが死亡し、相続人が子B、子C、子Dの時に、相続人Bが相続放棄した場合、子Cと子Dの相続分が増えます。これを寄与分とみて、子Cが死亡し、相続人が子B、子Dの時に、子Bは寄与分を主張できるでしょうか。
原則として、寄与分は認められません。
もっとも、先行する相続の類型、相続放棄の理由、相続放棄からの期間等を考慮して、寄与分を認める余地があるとする見解もあります。
先行相続の寄与分
例えば、Aが、父親の相続の時に、父親に対する寄与分を主張せず相続放棄をしたにもかかわらず、母親の相続のときに父親に対する寄与分を主張することはできません。
債務の保証
被相続人の債務を保証した場合や担保を提供した場合に、寄与分を認める見解もありますが、保証債務を履行した場合や担保権が実行された場合に限るとする見解もあります。